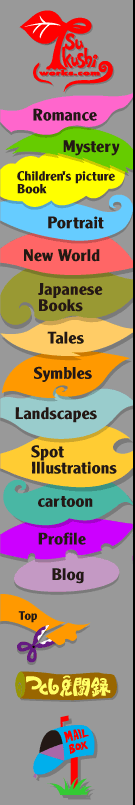| ダウンタウンにGreenwich House Potteryという100年の歴史を持つ陶芸教室がある。表に感じのいい小さな看板があるだけで、ぱっとめにはそこに工房があるなんてわからない。中実にいい雰囲気の場所だった。私はそこに2年間通いつめた。
人はなぜ土をこねるのだろう?指先に伝わってくる大地の触感。こねこねしているあいだにできてくる形。子供みたいになって体中粘土だらけにしながら、時間を忘れて没頭した。それは民族をこえた共通のよろこびなのか。ニューヨーカーもプエルトリカンも黒人もアジア人も、みんな夢中になって土と格闘していた。
そこには3種類の粘土とたくさんの釉薬があった。その中に日本の焼き物の名前がついたものもある。RAKU、SHINO、ORIBEなど。私はとくにSHINOが好きだった。窯から出してきた時のおどろき。いつも思いもよらない色や景色になった。
ニューヨーカーは基本的にフレンドリーだが、この工房に来ている彼らはどこか気むずかしい。めったに人の作品をほめない。しかし私の作品はよくほめられた。一度、先生のアパートに連れて行かれ「あなたの作品をいっぱい作って売りなさい」とまでいわれたことがある。「いや先生、私はイラストレーターなんですが...」と、あとずさりする。はっきり言って、そこまで褒められるくらいのものは作っていない。「先生、買いかぶりすぎ〜」と謙遜していたが、まわりをみわたして、なるほどとおもった。
ここだけのはなし、ニューヨーカーの作るお皿にはバリエーションがなかった。お皿と言えば、真っ平らなもの。コーヒーカップと言えば、寸胴の筒にでっかい取っ手をむんずとくっつけたもの。どれもがでっかく重たいものばかり。そう、それはまさにディッシュウオッシャーで、ガーガー洗っても平気なものなのだ。あのころは、家が揺れるくらいゴロゴロとおおざっぱに洗う機械しかなかった。日本にあるようないろんな形のお皿なんて洗えたものじゃない。まさにアメリカで売っていた食器とは、そういう形しかなかったのだ。だから彼らの頭に三角形のお皿や、アンシンメトリーなコップ、三つ足がついたお椀、なんて発想はこれっぽっちもなかった。そんな中で、それまで見たこともないようなものを作っちゃう私のアイディアに、先生はホレてしまったのだ。なんのことはない。日本人が当たり前に日々使っている食器なのだ。その時、私たちはいろんなものを見てきていると気がついた。
確かに陶器の歴史は、中国やヨーロッパからもたらされたものに違いない。しかしそれを吸収していろんな姿が出来上がった。志野、織部、備前、萩、益子、九谷、有田、清水、信楽、唐津......。一つの国でこんなに種類が豊富な焼き物がある国はあるだろうか?日本人の目はまさに肥えているのだ。
事務所の奥に図書室があった。陶芸作家の写真集がずらりとおいてある。そのほとんどが日本の作家のものだった。ニューヨークの陶芸作家にとって、日本の作家はあこがれだったのだ。講師をやっているおにいちゃんから、益子焼の濱田庄司の名前をよく聞いた。しかし写真で勉強するのと、私たち日本人がそれに触れて使っているのとでは大きな違いがあるのかもしれない。なぜなら、彼はただ濱田庄司の物まねをしているだけだった。もしこれが日本人なら、もっと何か他のテイストを混ぜ込んで、あらゆる姿に変えたに違いない。
日本人はファジーだとか、はっきりモノを言わないとか卑下されるが、そんなふうに簡単に決めつけてはいけない。そのとき私たちは一瞬のうちにいろんなことを考え、いろんな視点でものを見、しいてはいろんな民族の気持ちが分かるから、白か黒なんてはっきり言いきれるものではないと思っているのではないかと思う。だって、その心はお皿一つとってみてもわかるではないか。 |